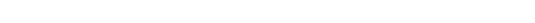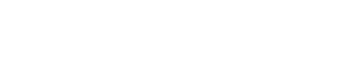第3回
テーマ:理解講座「難民が地域で暮らすということ」
日程:9月9日(土)
共催:認定NPO法人 難民支援協会
講師:吉山昌(認定NPO法人 難民支援協会 ディレクター・事務局長)
*
第3回目の理解講座では、認定NPO法人難民支援協会のディレクター兼事務局長の吉山昌さんを講師としてお迎えしました。前回と前々回にご登壇いただいたAAR Japan[難民を助ける会]が日本における難民支援に関わる老舗の団体であり、緊急事態が発生している海外の現地に出向いた活動を展開されているのに対し、1999年に設立された同団体は、いわば「駆け込み寺」のように日々、日本にたどり着いた難民たちの支援を行っています。

ご登壇者の吉山昌さん
吉山さんからは、全世界で避難を余儀なくされている人の総数、日本における難民申請者と認定者の推移など、統計に基づく現状が報告されました。
2016年に日本で難民申請を行った人は10,901人、そのうち認定されたのはわずか28人と、国際基準に照らした時に、日本においていかに難民の受け入れ体制が不十分であったかを痛感させられました。
また日本社会では、難民問題があまり認知されていないこと自体が大きな問題であり、それによる根拠のない誤解や偏見も根強いということが指摘されました。難民申請の結果が出るまでは平均3年と長い時間がかかるため、その間は衣食住もままならない生活が続きます。
彼らをサポートする際、難民支援協会は物質的な支援も行いつつ、彼ら自身の力と、協会以外の方々の力、その双方を引き出すことを意識しているということも明かされました。継続的に支え続けることは困難であるだけでなく、難民にとっても良いことではなく、地域のつながりの中で暮らしていけるようにすることを目指したいということです。

この点については、複雑な構造ゆえに時間がかかり、また共同作業によって初めて完成するグリーンライトの考案においても、難民にならざるを得なかった人々とともに生産的な時間を過ごすという意図があったのではないかと思わせられました。

理解講座の後半は、グループに分かれてワークショップを行いました。自分の住む地域で、シリア難民を受け入れることになったという設定のもと、どのように彼らを支援できるかを議論しました。

このワークショップでは、受入当日、受入から1週間後、1か月後、2か月後という異なる時間軸を想定し、それぞれの段階において求められるであろうことを考えました。各グループからは、難民のことを受け入れる前提として、彼らの宗教や文化など、彼ら自身ことを知ることが挙げられ、相互理解の大切さが共有されました。

日本において現状では少ない「難民」の受け入れ問題ですが、向後5年間かけて日本政府がシリア難民の留学生を5年間で150人受け入れると発表しており、初年度の今年はそのうち20人が来日するとも報道されています。また政府の取り組みとは別に、難民支援協会は民間の日本語学校などとともに、シリア難民の留学生受け入れを進めているとのことです。そのような状況のもと、日本社会においても難民問題への理解が深まることが望まれ、本ワークショップも参加者にとっては、わずかながらでも難民について考えるきっかけとなったのではないかと期待を寄せるところです。

*撮影:田中雄一郎
≫ 【Green light―アーティスティック・ワークショップ】開催日誌③
≪ 【Green light―アーティスティック・ワークショップ】開催日誌①
【Green light―アーティスティック・ワークショップ】各回アーカイブ映像はこちら(youtube)
【Green lightーアーティスティック・ワークショップ】開催日誌一覧はこちら