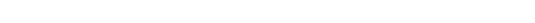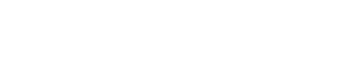第1回
第1回
テーマ:理解講座「ワタシが難民になったら」
日程:8月21日(月)
共催:AAR Japan[難民を助ける会]
講師:穗積武寛(AAR Japan[難民を助ける会]プログラム・マネージャー)
ラガド・アドリー(AAR Japan[難民を助ける会]支援事業部プログラム・コーディネーター)
第2回
テーマ:理解講座「ワタシが難民になったら」
日程:8月28日(月)
共催:AAR Japan[難民を助ける会]
講師:栁田純子(AAR Japan[難民を助ける会]支援事業部主任)
ラガド・アドリー(AAR Japan[難民を助ける会]支援事業部プログラム・コーディネーター)
*
第1回目と第2回目の理解講座では、講師としてAAR Japan[難民を助ける会]をお招きしました。AAR Japan[難民を助ける会]は、1979年にインドシナ難民を支援する目的で設立され、これまで38年にわたって60以上の国と地域で活動されてきた実績をもつ団体です。前半は、シリア出身の同団体職員ラガド・アドリーさんのお話しをうかがい、後半は、グループワークによるワークショップを行いました。

ラガド・アドリーさん
ラガド・アドリーさんは、大学時代に日本へ一年間留学した経験があり、その後はシリアに戻って家族とともに平穏に暮らしていました。レクチャー中には、シリア騒乱以前のシリアの日常生活を伝えるスライドが映されましたが、いずれも現在ニュースで流れる荒廃したイメージからは想像もつかない程に美しい光景です。そこには、われわれと同じく、平和で穏やかな日常があったことを、彼女が強調されていたことが印象的でした。
しかし、2011年3月15日より現在まで続く反政府運動ならびに、シリア政府軍とその反対勢力による武力衝突により、美しかった街並みは変わり果て、幸せな日常は奪われました。アドリーさん自身は日本で働いています。アドリーさんは、国により定められたいわゆる「難民」ではありません。しかし、当たり前だった日常が奪われ、帰りたくても帰れず、また家族と離れて暮らさなければならない状況に置かれた人々の思いは、難民認定の有無に関わらず共通の思いがあるのを感じずにはいられませんでした。
日本と変わらず平和であったであろう国で営まれていた日常が、突如として奪われてしまうことの恐ろしさが身近に感じられる話でした。

栁田純子さん(28日講師)
続くワークショップでは、5~6人ずつ、3グループに分かれ、グループワークを行いました。それぞれのグループがシリア人の一家族であるという設定により、事情が異なる家族構成や、その家族が抱える問題が書かれたカードが配られました。シリア騒乱が起きた時、家族皆でこれからどうするかを考え、話し合うことが求められたわけです。
選択肢は大きく分けて、①シリアに留まる、②トルコなどの近隣国へ逃げる、③ヨーロッパなど第三国を目指す、の3通り提示されました。また、向かった国でも、難民キャンプに入るか、入らないか、の二択が迫られます。
そもそも現実には難民キャンプに受け入れ可能な家族は1割ほどであり、また受け入れられた場合には、そこでの一時的な生活は保障されるものの、仕事をすることが禁止されているなど長期的な視点で考えた場合には難しい縛りも出てきます。

家族の条件を示すカードには、子どもの人数や、家族構成員の怪我や障がいの有無などが記されており、それにより、子どもの将来の教育のこと、物理的な障害などを総合的に考慮した上で、行く末を決定しなければなりません。
15分ほどの話し合いの結果、3グループが導き出した答えは、②トルコなどの近隣国へ逃げる、あるいは③ヨーロッパなどの第三国を目指す、が主でした。また難民キャンプに入るかどうかも意見が分かれました。

グリーンライト組立ワークショップの様子
正解や不正解はありません。日本において、ニュースでシリア難民のことを聞いても、どこか自分からは遠い国で起きている事件として、実感を伴わずに聞こえてくる人がほとんどだと思います。しかし、家族とともに幸せに暮らしていたラガドーさんが、今置かれている状況に思いを馳せ、また、家族単位のこととして難民となった場合に起こる問題を具体的に考えることによって、どこか遠くの他人事から、一気に身近な「自分ごと」として引き寄せてこの問題を捉えることができた時間となりました。
*撮影:加藤健
*掲載写真は全て8月28日開催のワークショップのものです
≫ 【Green light―アーティスティック・ワークショップ】開催日誌②
【Green light―アーティスティック・ワークショップ】各回アーカイブ映像はこちら(youtube)
【Green lightーアーティスティック・ワークショップ】開催日誌一覧はこちら